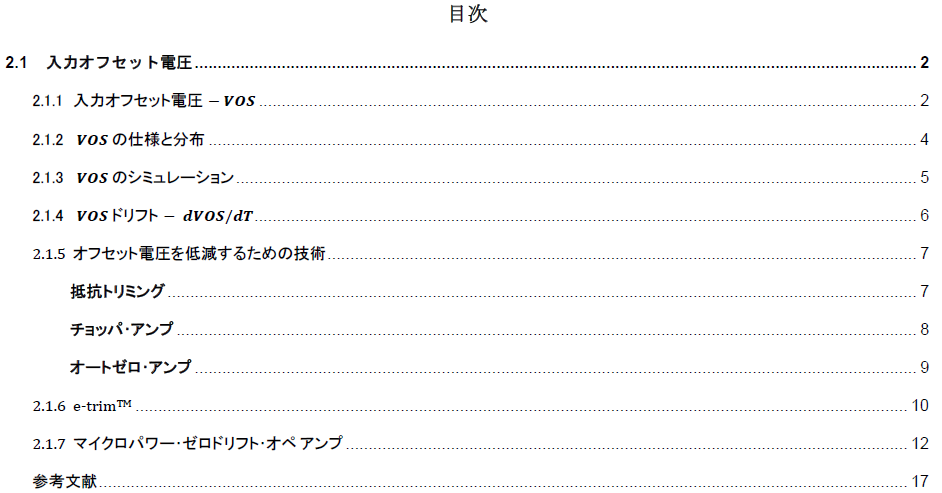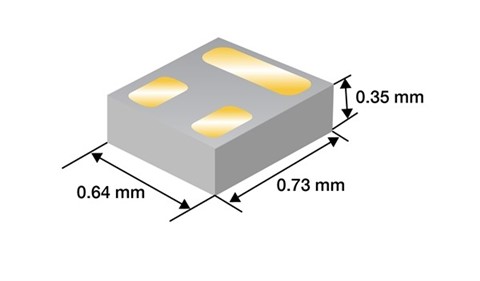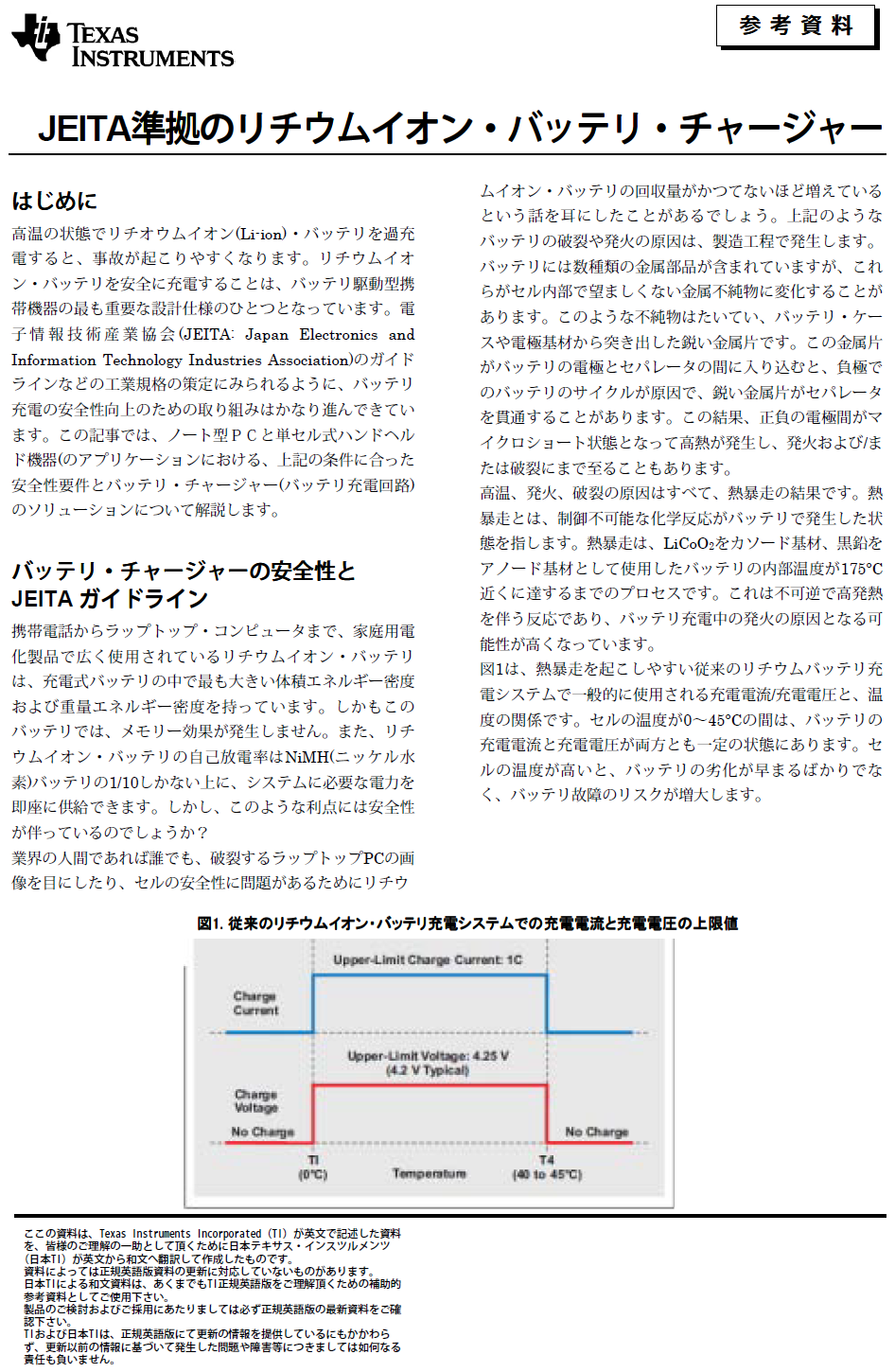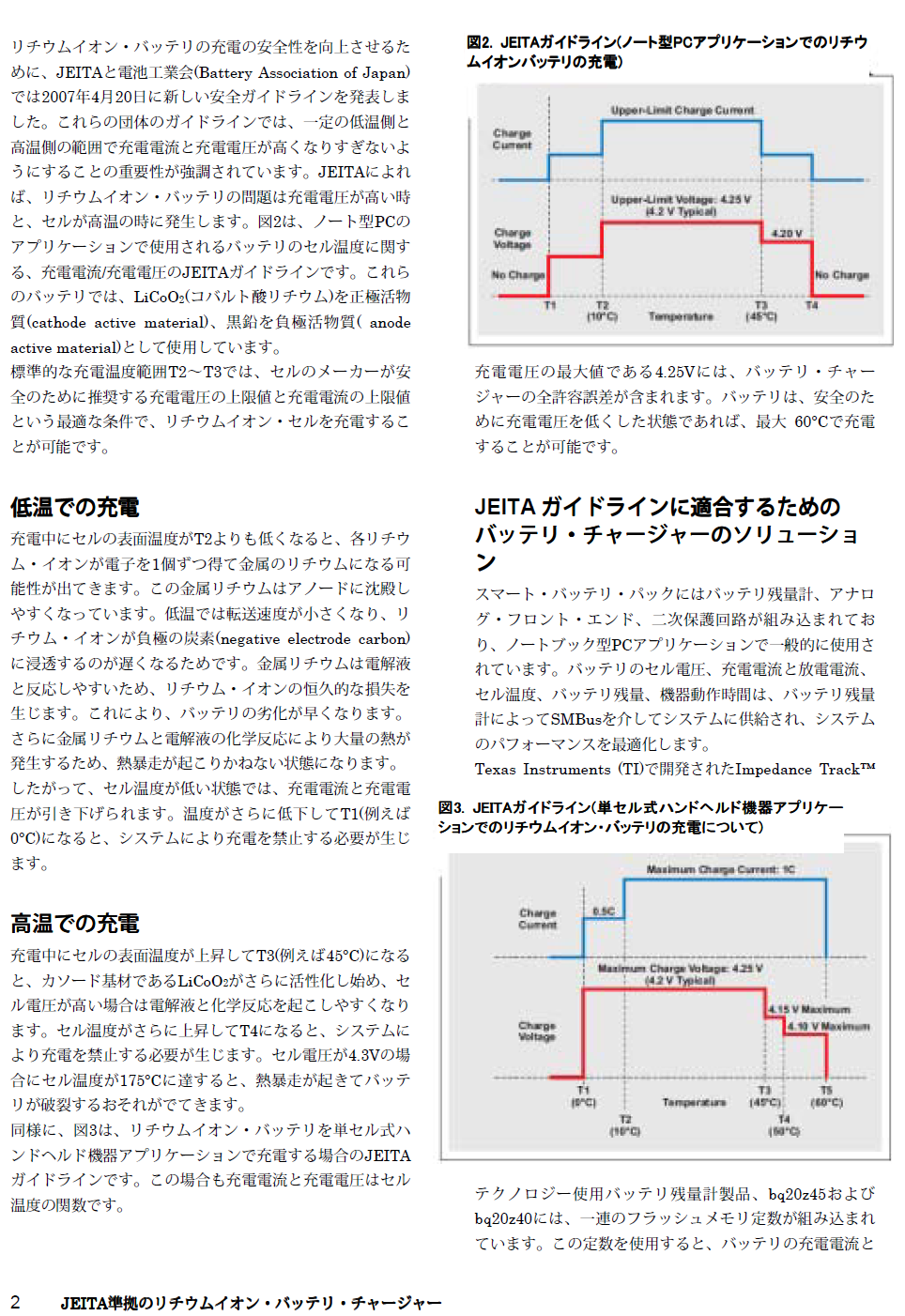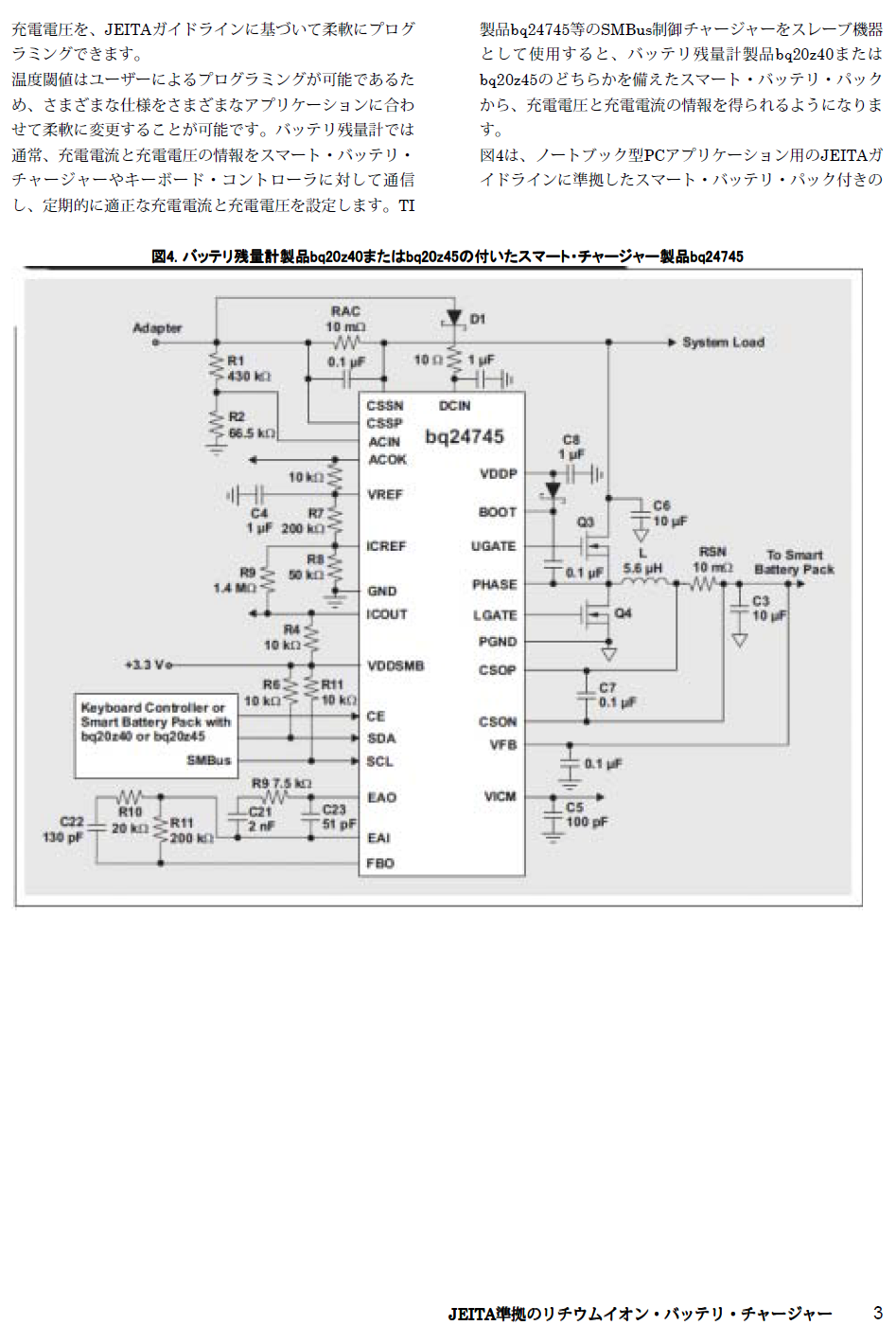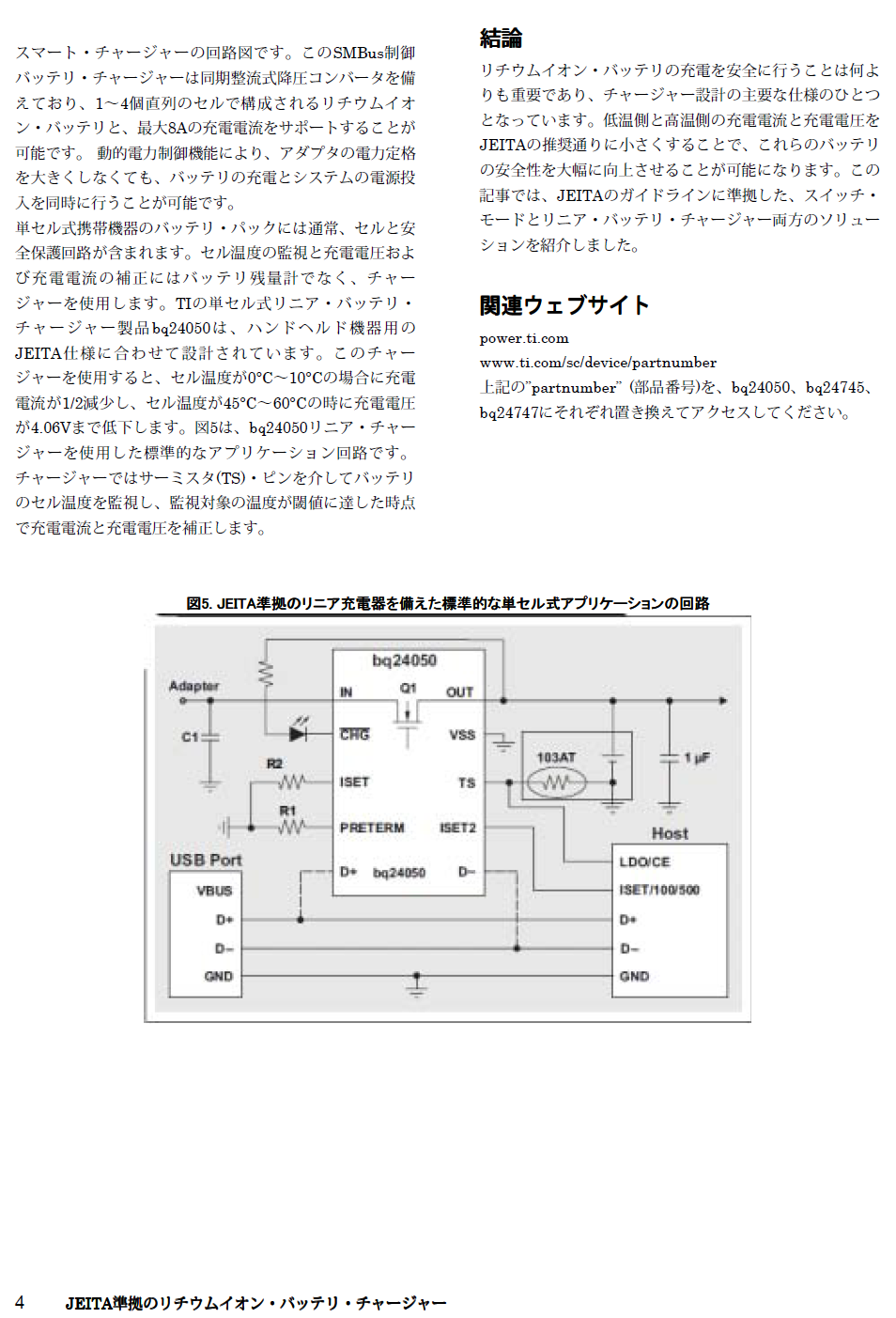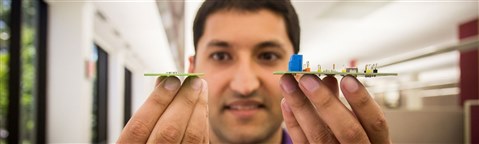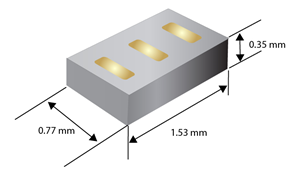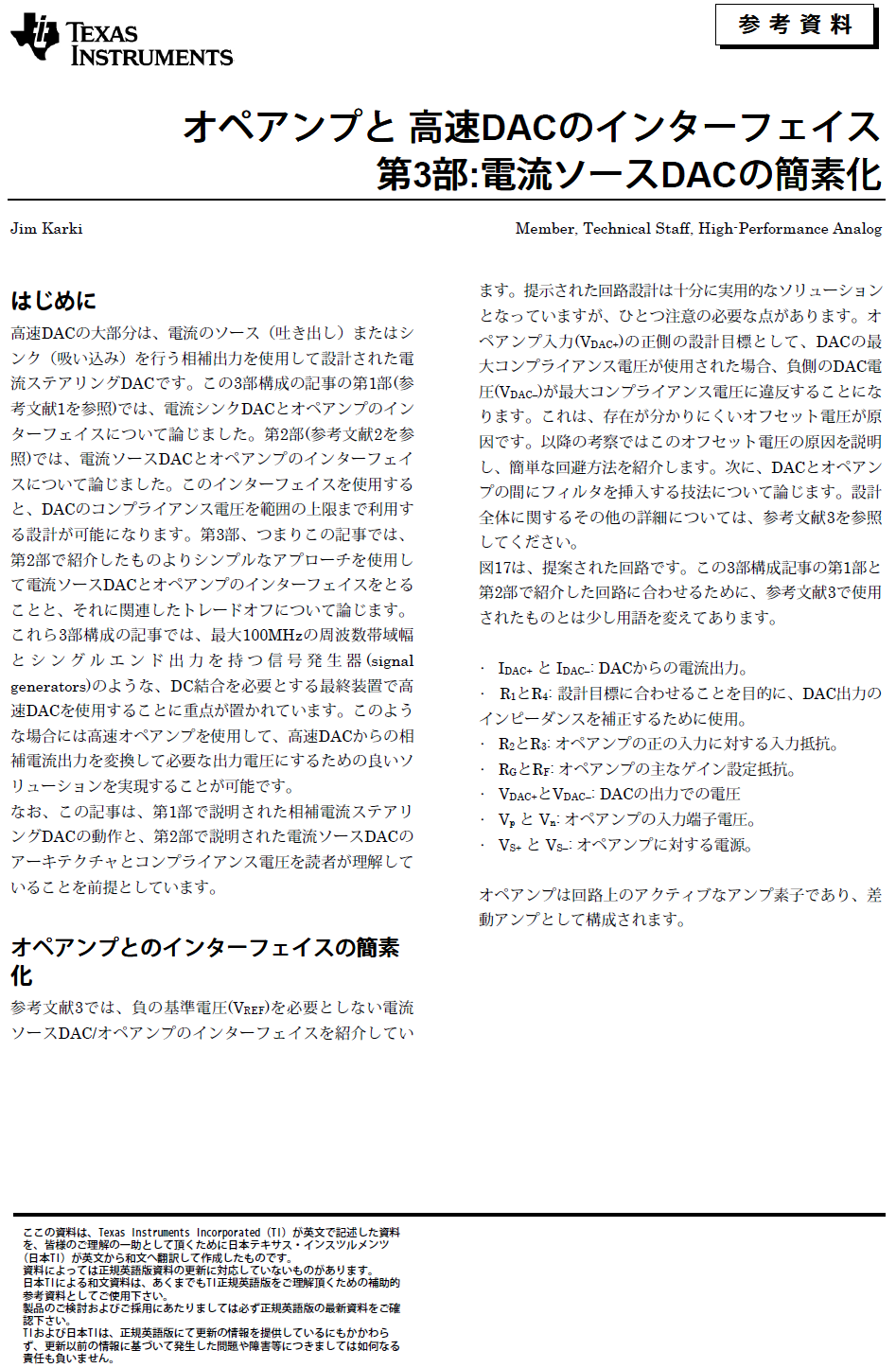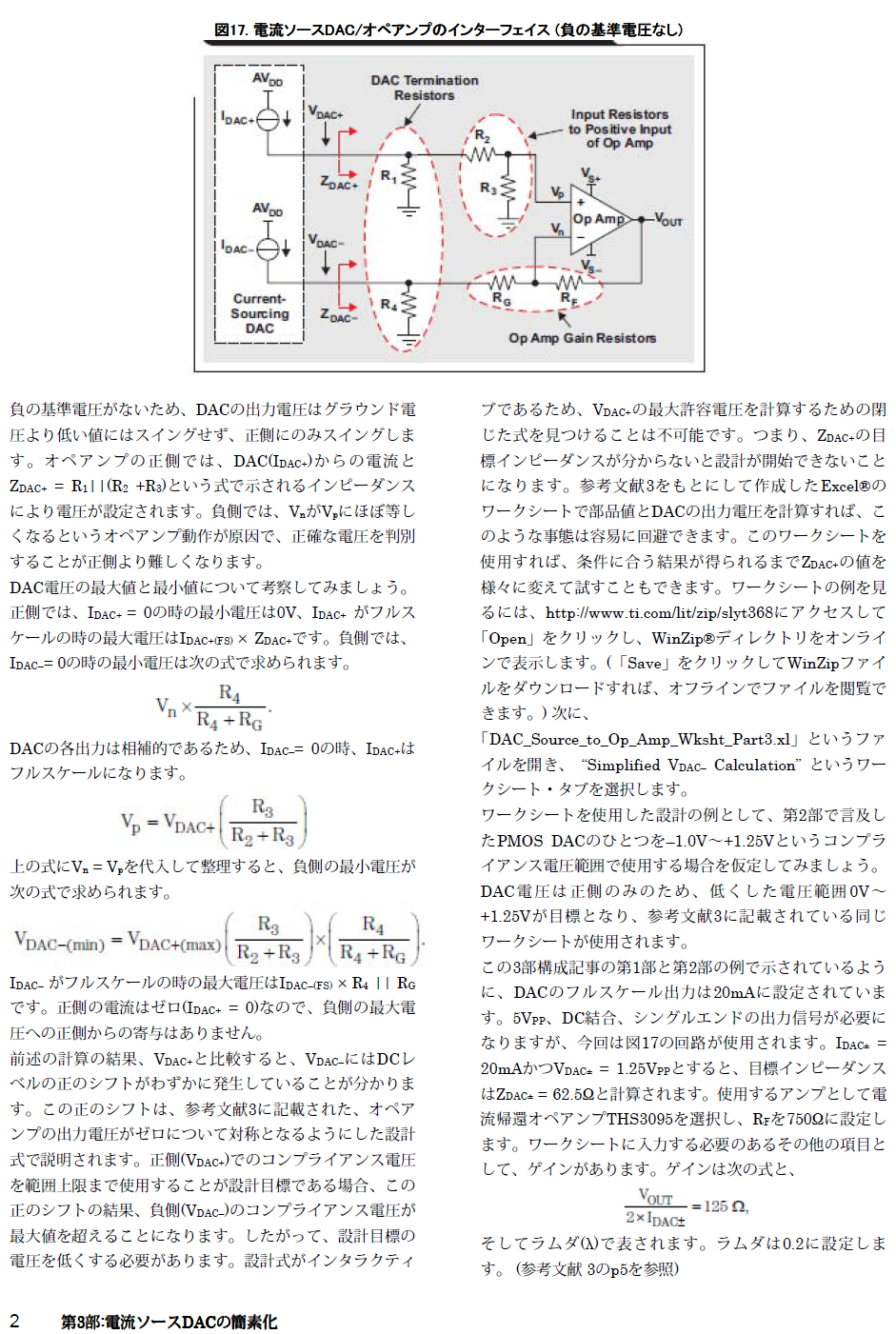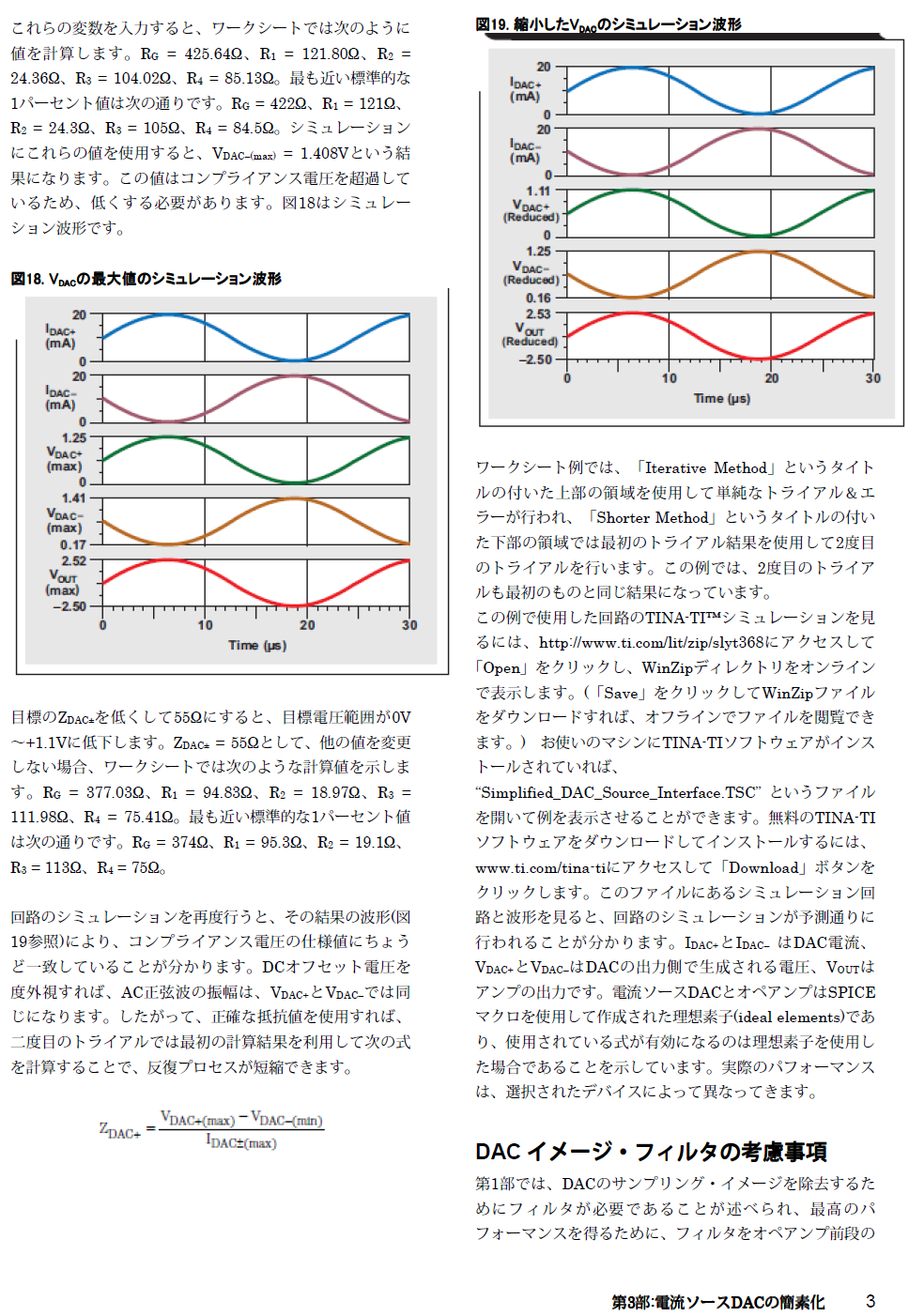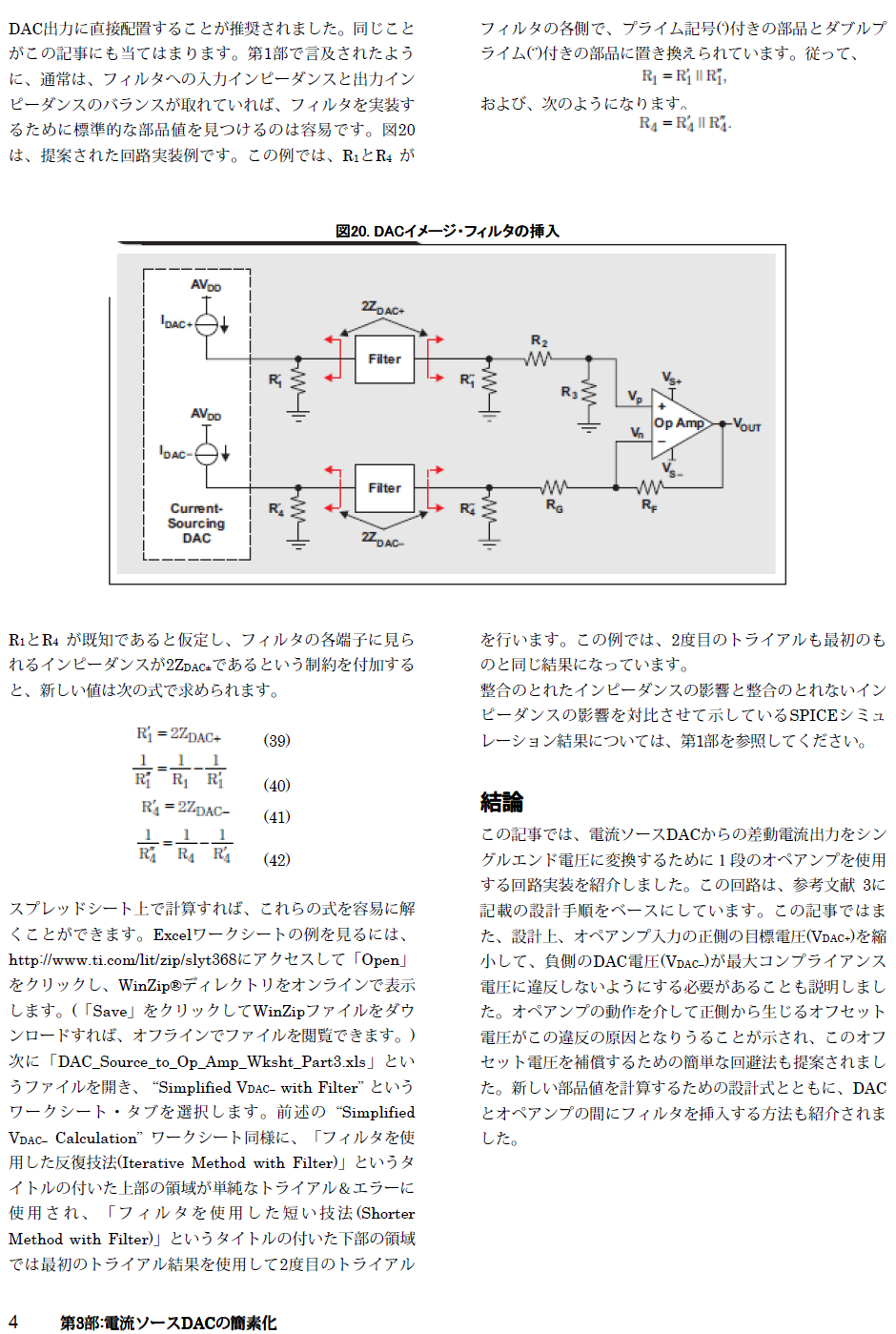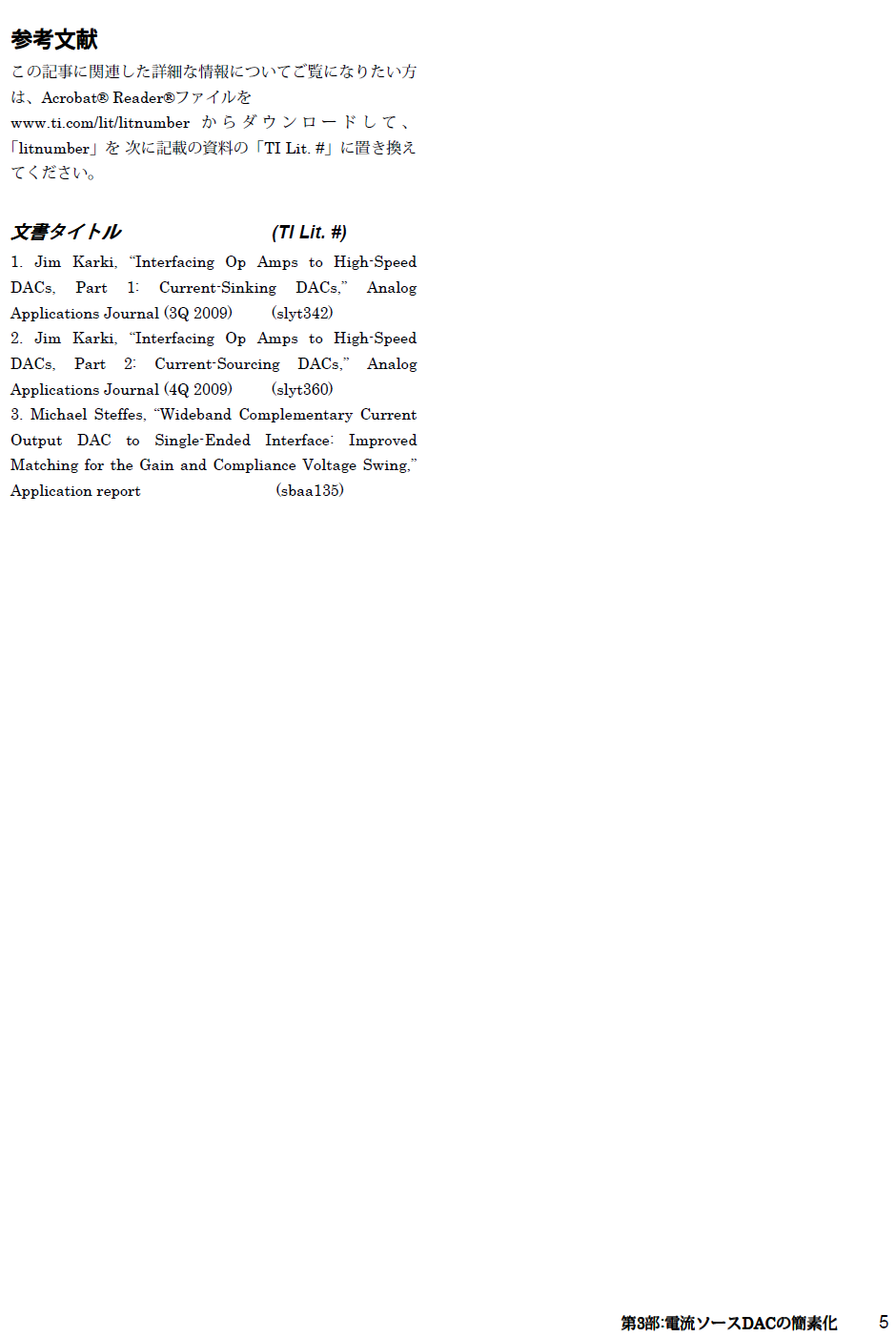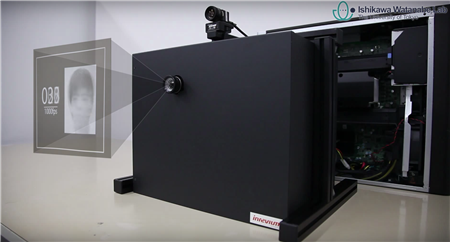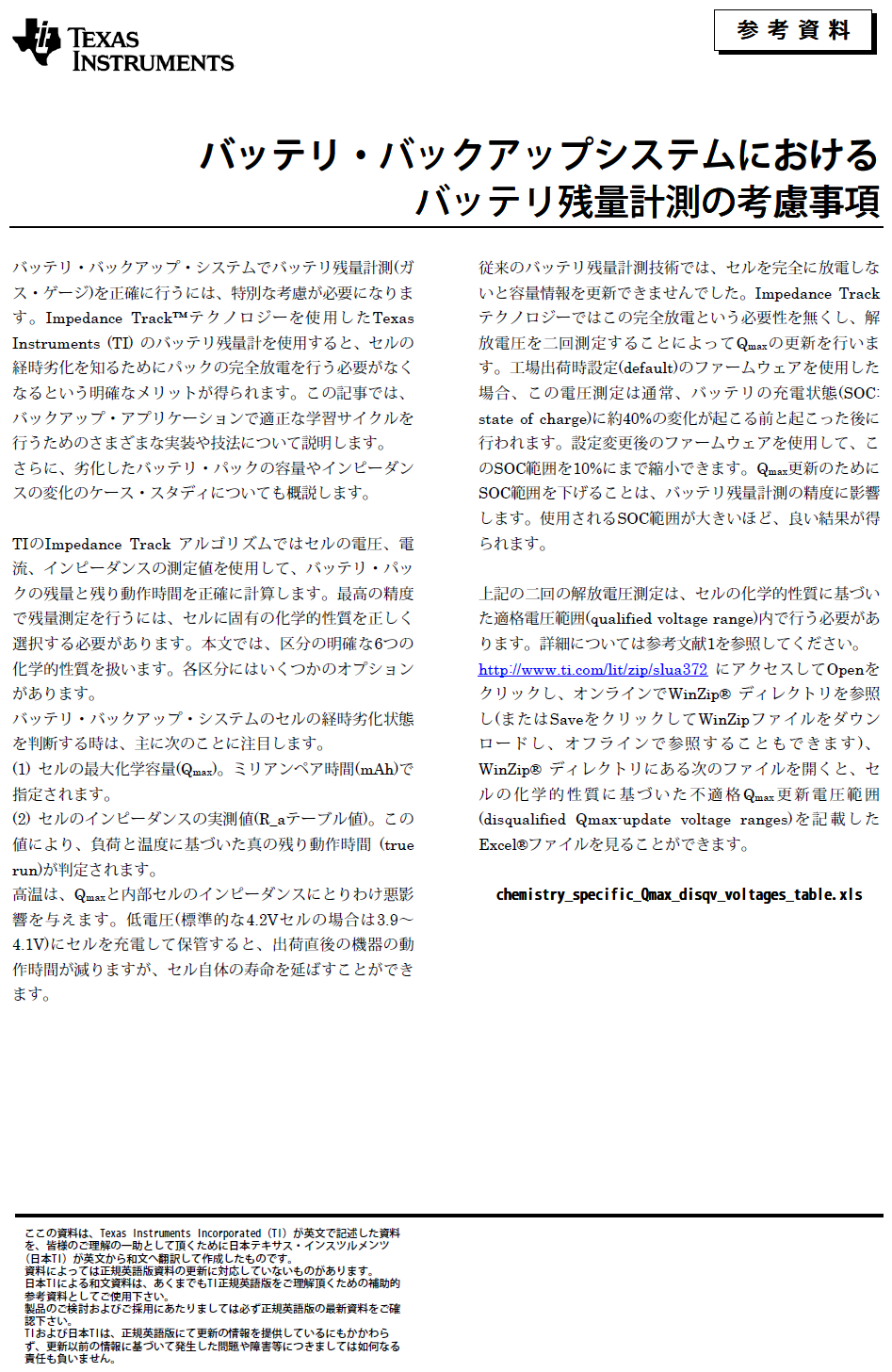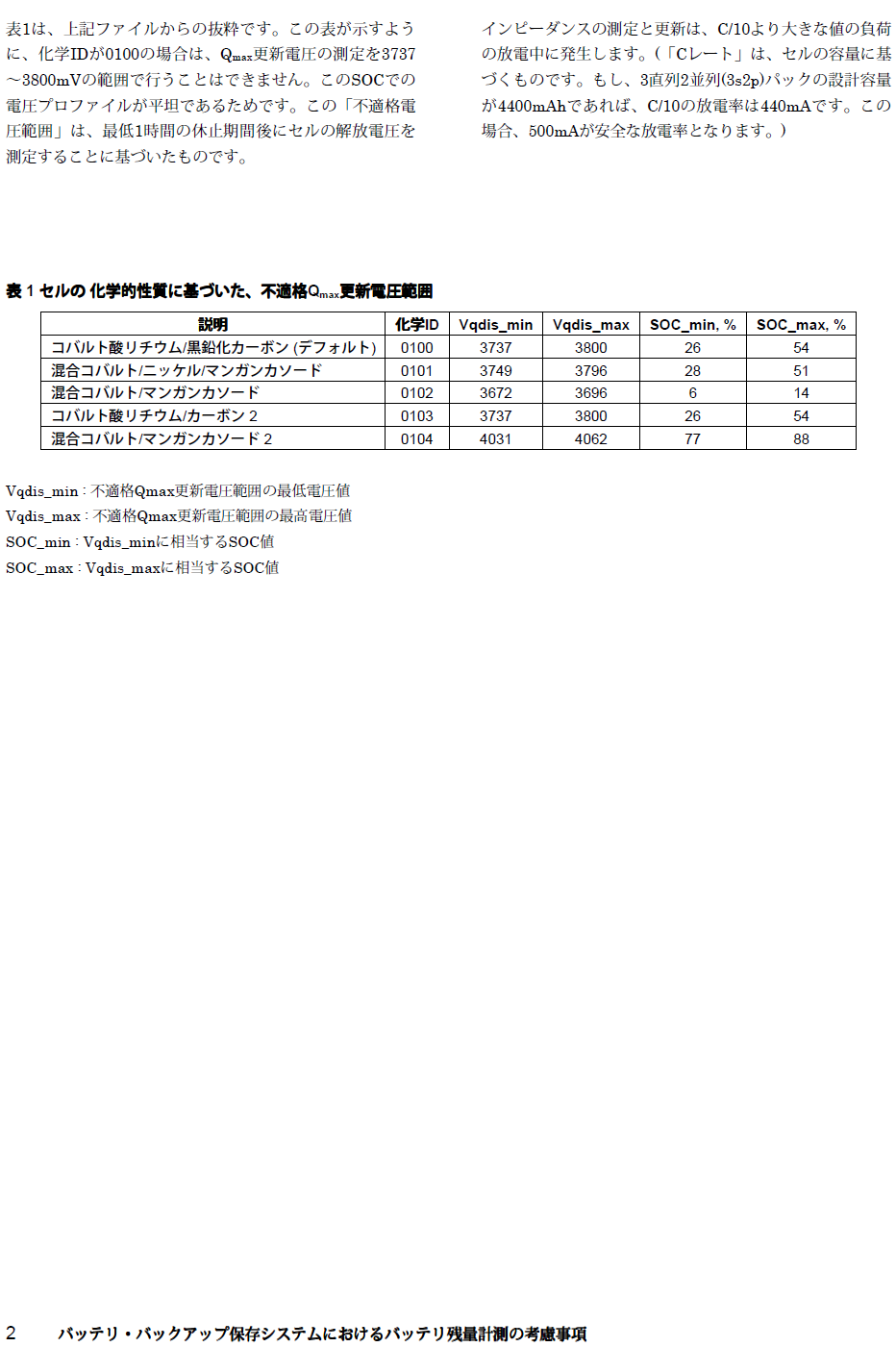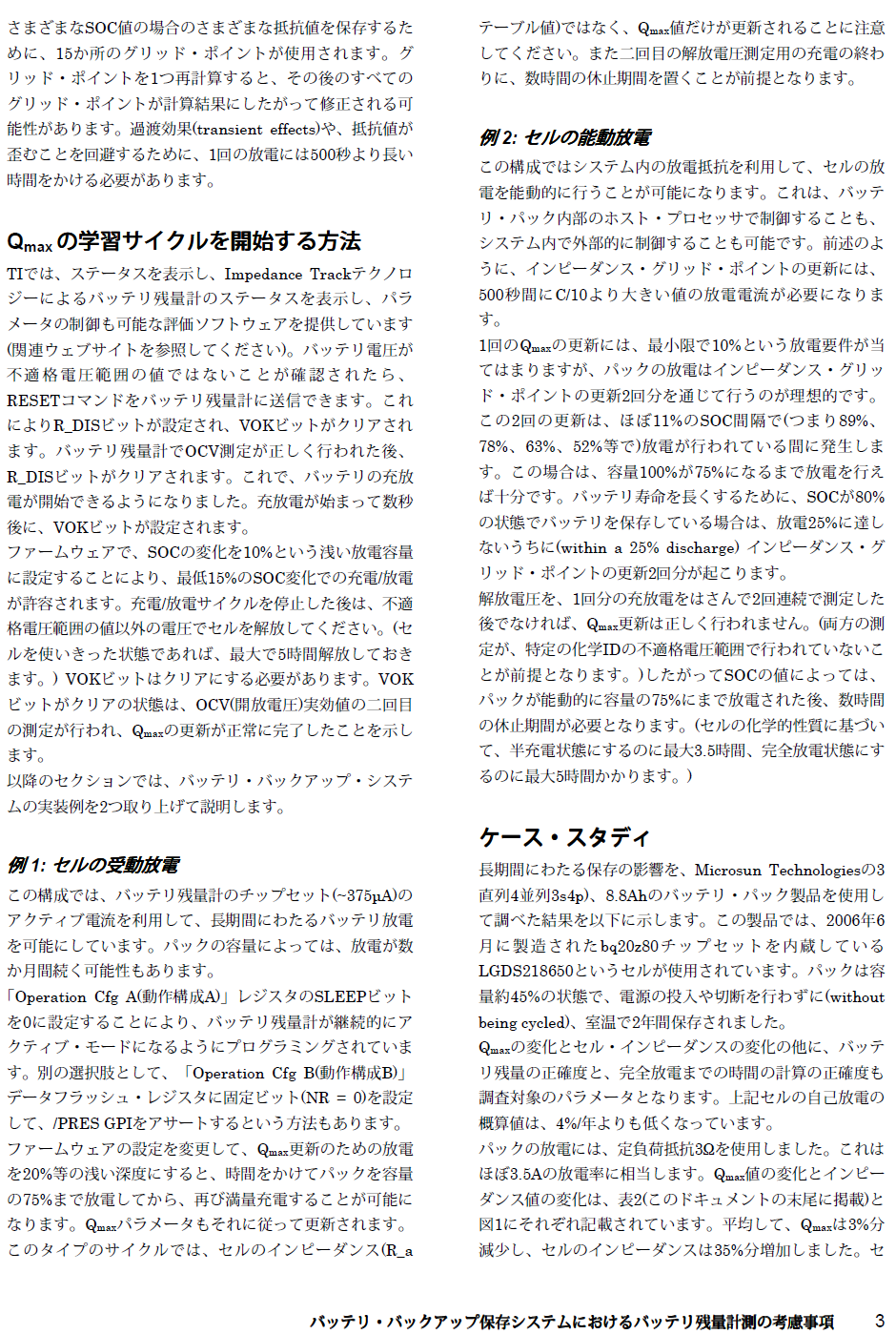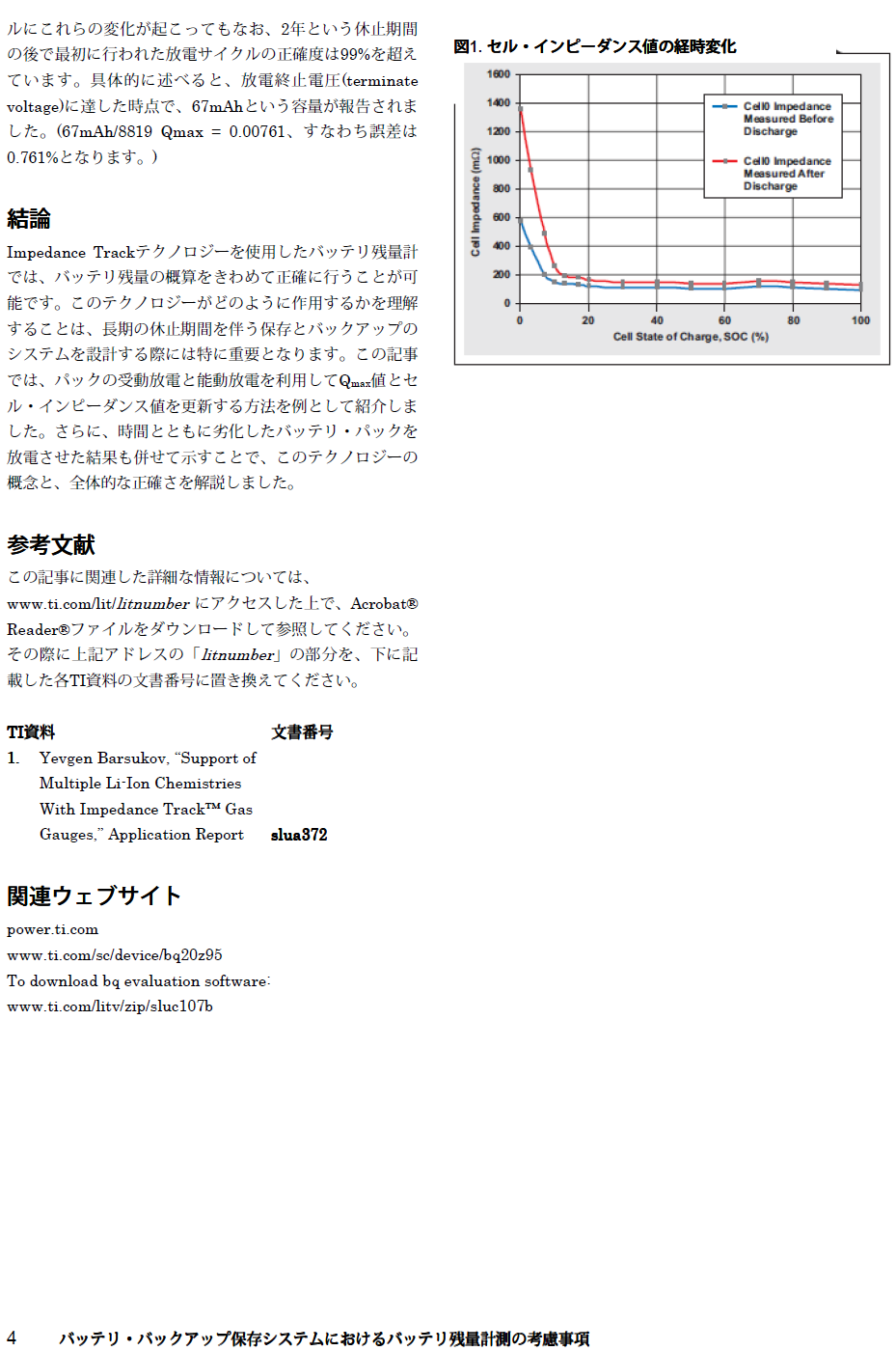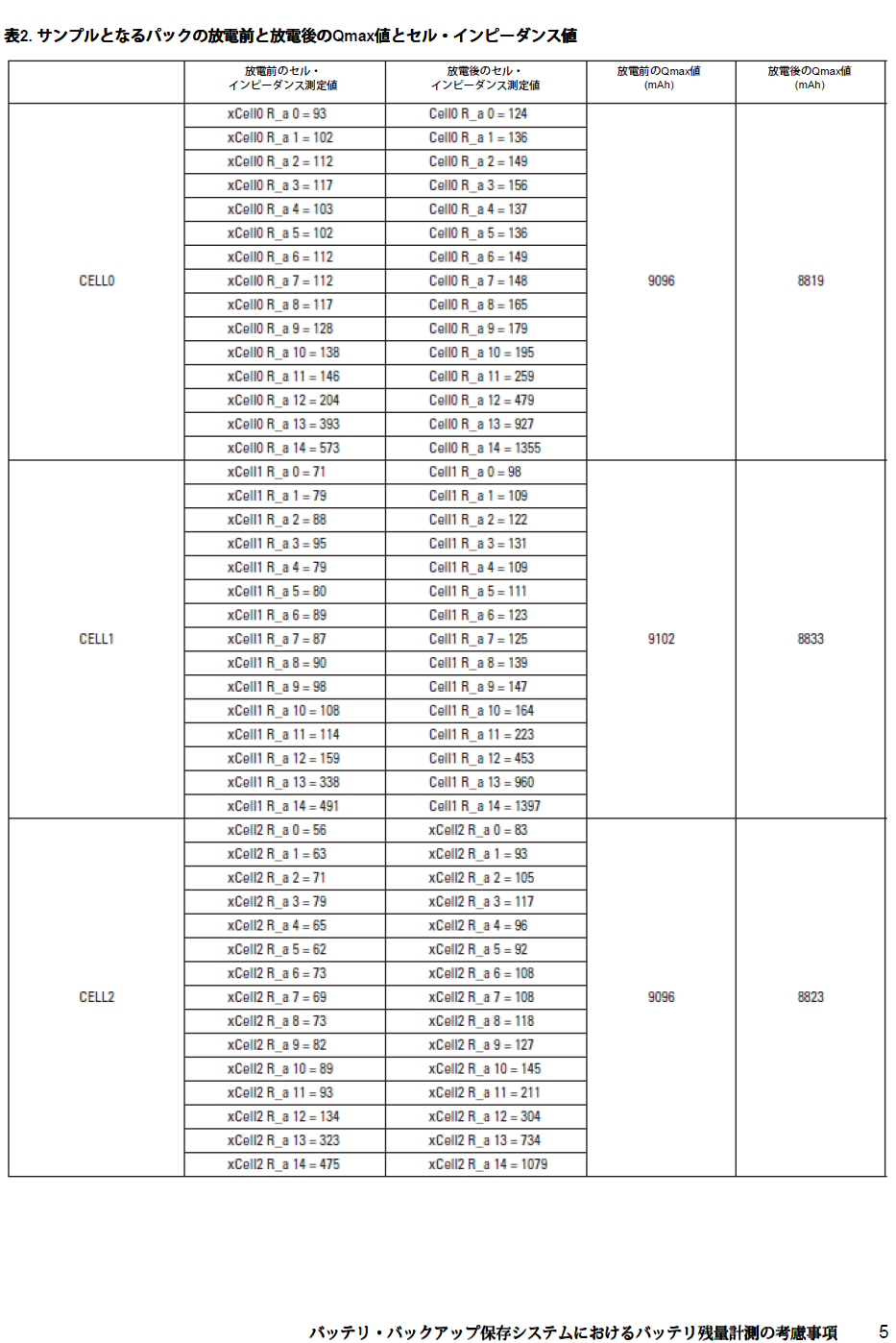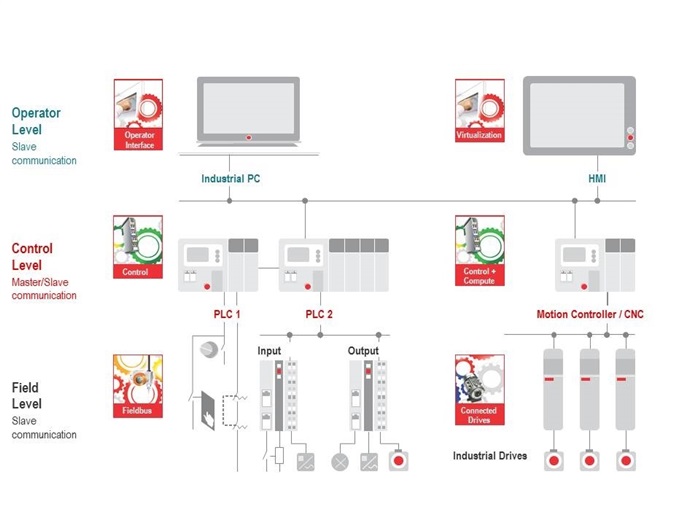このブログはアナログシグナルチェーンの基本素子とも言うべきオペアンプの基本理論と応用回路技術の習得を目的とします。本格的な電子回路シミュレーション・ツールである TINA-TI を自分の手で実際に動かすことで直感的な理解が得られるよう工夫しています。 今回は、実践編として入力オフセット電圧を取り上げます。
e2e.ti.com/.../7571.TINA_2D00_TI_5F00_OPA_5F00_11_5F00_20160709.pdf← クリックしてダウンロードして下さい
TINA-TI によるオペアンプ回路設計入門 ← クリックすると ブログ本体 にジャンプします。